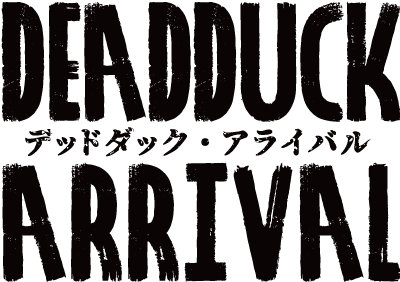DEAD DUCK:役立たず、もう見込みのないもの
あらすじ
無能な探偵・有能な魔術師/レオン=アライバルが、潰れかけの探偵事務所を救うため、魔術師として仕事を受けては絶体絶命の大変に遭うのだった。
試し読み
 <キャラクターカタログ・特別掌編>
<キャラクターカタログ・特別掌編>
全部読める!
レオン=アライバル探偵事務所は年中経営が低空飛行であるので、些細な仕事でも選り好みすることなく引き受けねばならない。所属する唯一の探偵であるアライバルもそれを承知していたため、行方知れずの猫探しという、労力のわりに報酬が見込めないような依頼を請け負うに至った。
通り一遍の迷い猫対策を試して効果がないのを確認した後、聞き込みという当てどない工程に乗り出したアライバルは、すでに集中力を欠いていた。実を言えば探す手段自体はいくらでもあるのだが、そうした方法を用いることは主義に反する。なので、より探偵らしい方法でもってことにあたることにした。つまり、推理だ。
猫が脱走するのはよくある話だ。依頼人は庭で猫を遊ばせていたそうなので、いついなくなってもおかしくはない状態だった。が、他方、防犯に気を配っていなかった、という話も聞いている。外から入ってきて猫をさらった可能性もある。猫を誘拐する目的が何かと言えば、売買か身代金か、もしくはただ単にその猫が欲しかっただけか。
犯人から連絡がないのだから、恐らく身代金目的ではない。ペットの売買組織というのはいかにもあり得そうだが、そうなると見つかるあてがなさそうだ。できれば、近所の人間が犯人であってくれた方がありがたい。
と、想像を膨らませていたのが悪かった。
「証拠はすべて出揃ってる。観念した方がいい」
と、聞き込み先の玄関口でなぜか口にしてしまった。
完全に頭のおかしい発言であることはさすがのアライバルも分かったので、すぐさま弁解しようとしたのだが、その前に相手の顔が見る見るうちに強張って、気が付いたら胸に衝撃を受け――そこに、ナイフが突き立てられているのが見えた。
「……しまった」
血の付着したナイフを流しで洗いながら、アライバルは嘆息する。刺された傷を治したために、全身を倦怠感が襲っていた。
家の中に猫は見当たらなかった。どうも、まったく別の事件の犯人だったらしい。とっさに記憶操作の魔術を使ったせいか精度が甘く、何の事件の犯人かも聞き出せない状態になってしまった。少しすれば多少は記憶も戻るだろうが、そこで犯行を白状させてもそれは探偵の仕事ではない。放っておくしかないだろう。しかし、完全に、これで集中が切れてしまった。とりあえず今日は切り上げて、飯でも食べに行くことする。
猫はまだ見つからない。
 <オリジナルタロット企画・特別掌編>
<オリジナルタロット企画・特別掌編>
全部読める!
「『
頭上から笑みを含んだ声が落ちかかった。
首をひねって無理に見上げなくても誰なのかが分かったし、そう言いたくなるのも理解はできる。
アライバルの足首と後ろに回った両腕は、しっかりと縄で縛られて繋がっている。上から宙吊りにされてぶら下がっているそのさまは、まさにあのカードにそっくりだ。自分では自分のことは見えないけれど、恐らくはそうだろう。
「正位置の意味は確か、忍耐、試練、献身、自己犠牲……
読み解くところによると、刑罰ではなく
「レオン=アライバル。
……それから、俺は魔術師じゃなくて探偵だ」
苦々しく訂正する。
実際、今の自分が魔術師と胸を張って言えるかは怪しいところだった。
吊り下がった頭の下、魔法円が輝いている。縄ではなくこの魔法円がアライバルを拘束し、脱出のすべを奪っていた。ふだんから身を守るために展開している術式の類もすべて休止している──つまり、ただの『吊られた男』だ。
「タロットよりも生身の俺に目を向けてほしいね。あんたにはぴんと来ないかもしれないが、人間が逆さ吊りにされたままだと、色々とよくないことが起こるんだ」
経営の傾いた事務所を救うため、馴染みのエマリーから依頼を受けたのは数日前のこと。怪奇現象が起こっている廃屋を調査してほしい、というどこかで聞いたような内容にうすうす嫌な予感はしていたのだ。
結果として、その予感は別の形で当たり、アライバルはこうして罠にかかることになった。すでに、吊り下げられはじめて数時間が経っている。
「落とし穴に落ちるのは人生で二度目だ。串刺しになるのはもう御免こうむりたいと思っていたが、逆さ吊りも最悪だな。
いいかい、目に見えて外傷がないだけで、相当まずい状態なんだ。心臓にゆく血液が多くなり、負担がかかって、心臓から血が送り出せなくなる。つまりは酸素が運搬できなくなる。目にも負担がかかって眼圧が大きくなりすぎ……実のところさっきからよく見えてない。あんたの無駄にいい顔も、このままだと二度と拝めなくなるかもしれない。できれば助けてもらえると嬉しいんだが」
「……お前、本当に酸欠なのか?」
「喋るたびに全身が痛いよ」
なぜか呆れを帯びた声に、アライバルはきっぱりと答えた。小さいため息が返ってくる。
「まあ、いいだろう。お前がその状態じゃあ、僕の相手をできそうにないからな。
ひとまずは、使える状態になってもらおうか」
「ちょっと待」
助け方に注文をつけようとしたが、もう遅かった。
投擲された剣は、アライバルを吊り下げる縄と魔法円のついでに、アライバルの喉笛までしっかりと切り裂いていった。
もつれそうになる足を忌々しく罵りながら、森の中を駆けていく。
足元は岩や石がだんだんと多くなり、人間の踏み固めた道の態を為さなくなっていた。人間どころか獣の気配さえなく、胸の悪くなるような肌の粟立つような強い殺気だけが、ただ辺りに満ちている。
どんな生き物だろうが、まともな神経さえ持っていれば、自分が標的にならないうちにさっさとこの場から逃げ出しているはずだ。
逃げてきた方向のまずさについて、今さら後悔する余裕はなかった。まずかったと言えば、もっと前の段階からだ。荒く息をつき、胸元を押さえる。
その上にこの空気だ。殺気と、殺意と、抑えられない喜悦に満ちている。
小枝を踏み割る音にすらびくつくほどに全身が緊張させられていた。逃げ回るだけではどうにもならない、逃げ切ることなど不可能だ、と頭では判断していながら、逃げ続けることしかできないでいる。
どうしてこんなことになったのか。なぜこんな選択をしてしまったのか。
……実のところ、全て分かっていた。それでも、問わずにはいられなかった。だからこそ忌々しい。
足がもつれ、転びそうになるのを踏ん張って顔を上げる。視界は狭くぐらついて、何もなくとも森の中、倒れ込んでいきそうになる。
それを繋ぎ止めるように。
背後から飛んできた剣が、首筋から喉元までを抵抗なく貫き通した。
「きわめて初歩的なトリックです」
アパルトメントの窓は開け放たれて、薄い綿のカーテンが夏の風にゆらゆらと揺れている。木造りの椅子に浅く腰掛けた男の顔色は、日に焼けているのにも関わらず――この気持ちのよい昼下がりにも関わらず――すぐ見て取れるほどよくなかった。
肩幅ほどに開かれた膝の上に、それぞれ手が置かれ、時折落ち着かなげに力を入れたり、胸元へ引き戻して手指の具合を確かめたりしている。右手の薬指には、年季の入った結婚指輪が嵌められていた。
「……トリック」
たっぷり間を取った後で、男がかすれた声を出す。そのかたく強張った顔に陰影がさしているのを、アライバルは部屋の中央に背筋を伸ばして立って見つめていた。浅黒い顔に微笑を浮かべ、相手に向かって手を差し伸べて見せる。
「ええ、奥方は非力な女性であり、アパルトメントに取り囲まれたプールのど真ん中に、男性一人の死体を痕跡もなく運ぶのは難しいように思われるかも知れません。いや、男だとしても、死体を運ぶのは手間です。
しかし彼女は、それをちょっとした工夫で乗り越えたのです。何の変哲もないロープを使って」
アライバルはそこまで言ってから、一拍間を置いて相手の表情を窺った。男は困惑しきった表情でこちらを見つめている。さもありなん。アライバルは鷹揚に頷いて見せると、再び口を開いた。
「プールサイドにはラダーハンドルという、プールに安全に入るためのはしごがありますね。当然、人間が使うものだから、人が通れる程度の横幅になる。
奥方はそこにロープを通し、部屋まで二本のロープをぴんと伸ばした。そして、男性をそこに括り付けて下まで滑らせたんです。
水の傍まで持って来ればあとは簡単。プールの真ん中に持ってきて、奇妙な殺人の完成というわけだ」
部屋の中に、永遠とも思えるような長い沈黙が落ちた。
アライバルは自分の披露した推理の余韻に浸るように瞑目する。
「…………セニョール・アライバル。ひとつ、よろしいですか」
「何でしょう」
沈黙を破ったのは男の方だった。かたく平坦な声。ひとつの罪がつまびらかにされたのだ。おののき感情を失うのも当然だろう。アライバルは腕を広げて見せる。男は唇を震わせ、言葉を続けた。
「私がお願いしたのは、殺人ではなく、妻の浮気調査なのですが……」
「そうでしたっけ?」
再び、沈黙。
アライバルは首をひねった。確かに、そうだったような気がしなくもない。浮気調査を途中までしていたような記憶がある……おぼろげながら。そういえば、途中でつまらなくなって、ちょっと方向を転換したような。
男は疲れたような深いため息をついた。
「……妻は、私が見ていないところで、浮気ではなく殺人を?」
辛抱強く、分かりの悪い子供に言い聞かせるような、念入りの確認をするような口調で問いかけてくる。雲行きが怪しくなってきた。
むろん、自分で雲行きを怪しくした自覚はある。
妻が殺人者であるなどと、彼にはにわかに信じがたいはずだ。当然、そういう質問をしてくるだろう。
だが、困ったことに、アライバルは重要な事実を思い出していた。そういえば、別に殺人などは起こっていない。
探偵に振られる日々のなんでもない仕事――浮気調査とか迷い猫探しとか――の多くはなんだかんだ言って殺人に繋がるはずなので、まだ、と言っていいかも知れないが、それを男に面と向かって言うのはまずい気がした。
「ええと、それは何というか、言葉のあやというか……」
「…………つまりあなたは、人の妻を勝手に妄想で殺人者呼ばわりした挙句、私にその妄想を、つまびらかに、話したと」
男の声はすでに、地の底から響くようになっている。過ごしやすいはずの涼しい風が、妙に冷え込んで感じられてきた。アライバルは目をうろうろと泳がせた後、気を取り直し、満面の笑みを浮かべて告げる。
「まあ……そういうことになりますね!」
「――」
男は、アライバルの言葉を聞いて、がっくりとうなだれると、やがてわなわなと震え出した。そして。
「帰ってくれ! へぼ探偵!!」
……というわけで、アライバルは怒号とともに依頼人の家から叩き出され、アパルトメントの扉の前にいるのである。
上を見上げると、開け放たれた木枠の窓に白いレースのカーテンが揺れているのが見えた。その奥に、いたく立腹した様子の依頼人の姿もある。
一体何が悪かったのか、いまいちよく分からなかった。この上なく上手くできた推理に思えたのだが。事実でないことを除けば。アライバルは妖精に化かされたような気持ちで、色とりどりのアパルトメントが立ち並ぶ通りを見回した。
午睡に最適な、実に気持ちのいい昼下がりだ。
空には雲一つなく、時折涼しい風が通り抜ける。日陰などにいると、すでに肌寒いほどだった。追い出される際にくしゃくしゃにして抱えていたジャケットを、鞄を持ったまま器用に着込みつつ、アライバルは家の影から日の当たる石畳の通りへ降りてくる。……返す返すも、どうしてこんなことになったのだか。ごくごく真面目に、仕事をしていたはずなのに。
「あっ」
ふと思い出して、ブリーフケースを開く。黒い革の鞄の中には、大きな封筒、さらにその中には体裁の整った報告書と、何枚かの写真が入っていた。
――そういえば飽きる前に、一応の体裁を整えていたような覚えがある。報告書には詳細な個人の足取り。写真には、依頼人の妻である女性と、依頼人ではない男性がさも親密に手を繋いで歩いているさまがはっきりと写っていた。男の身元も調査済みだ。
「セニョール・ピンタード!」
アライバルは書類を封筒に戻して、窓に向かって掲げて見せる。
「すまない、まさに今思い出したんですが、やっぱりちゃんと調査していましたよ、セニョール! 間違いなく、あなたの奥方は浮気してる!」
返事はバケツ一杯の水だった。
頭上から塊となって落ちてきた冷たい水をすんでのところで躱し、アライバルは目を瞬かせた。よく考えたら、往来で叫ぶことではなかったかも。
「……ええと、後でお宅に郵送しておきます」
遠慮がちなその声が、依頼人に届いたとは思えない。
頭上で窓のぴしゃりと閉まる音に大袈裟に身を竦めると、アライバルは封筒を鞄にしまい込んで、ジャケットに飛んだ水滴を払った。
果たして報告書は受け取ってもらえるか、受け取ってもらえたとして、つつがなく依頼料は振り込まれるか。いずれにしても、この依頼人とは、もうまともに会話してもらえなさそうだ。
深々と嘆息し、何が悪かったのかと首をひねりながら、アライバルは石畳の通りを歩き出した。どこかで一杯、ひっかけてから帰るべきかも知れない。
――レオン=アライバル探偵事務所は、目下倒産の危機の中にあった。
そもそものところ、依頼がない。ポストにはチラシや公共料金の督促状ぐらいしか入っておらず、来るメールも迷惑メールばかり、電話が来たかと思えばセールスの電話で、事務所を訪れる客もなく、閑古鳥が鳴きっぱなしだ。たまに依頼を受けても、なぜか依頼人を怒らせてしまって、報酬がろくろく入らないこともある始末だった。
本来ならば客が座るはずの革のソファに仰向けに寝転がって、アライバルは肘かけを枕にぼんやりと天井を見上げていた。古めかしいシーリングファンが緩やかに回り、部屋の中の温い空気をかき回している。いくら首をひねって見ても、何が悪かったのか全く分からない。
身を起こして、事務所の中を見回す。
およそ、探偵事務所に必要なものはすべて揃っていると言っていい。仕事机に応接用のソファ、ブラインドの下りた大きな窓と天井のシーリングファンライト、観葉植物、それから資料をまとめた本棚。ノートパソコンに印刷機があるのが多少今風過ぎるが、おおむね雰囲気は出ている。悪いものは特にない。だというのに、なぜ経営がうまくいかないのか。
……探偵になるのは、子供の頃からの夢だった。夢を叶えたはいいものの、そのあとがうまくいかない。世の中、ままならないものだ。
ううん、と、アライバルは意味もなく呻いた。
考えていても仕方がない。先程受け取ってもらえなかった調査資料はポストに投函したものの、それで依頼料が振り込まれなければ本格的に倒産の危機だ。今はとにかく、金を調達する必要がある。……あまり気は進まないが、仕方がない。
事務所の入り口に『本日休み』のドアプレートを引っ掛けて、扉の鍵を閉める。ブラインドを締めて明かりを遮ると、アライバルはソファまで戻ってきて掌を上に向けた。
しまっておいた本を取り出すのには、呪文の一つも必要ない。
広げた手の上に、モロッコ革で装丁された青い書物を受け止めて、アライバルは陰鬱な表情でページをめくり始める。
黄ばみ、黒ずんで劣化した紙の上に、美しい光の尾を引きながら、新たな文字が次々と描かれていった。人魚の聲の回収、竜の鱗の調達、増えすぎた魔法生物の処理に、旅行にする間に留守番させねばらならない火蜥蜴の世話……といった具合にだ。
魔術やまじないと言ったものは、かつて歴史の表舞台から、まやかしとして放逐された存在だ。
しかし、それらは幻や迷信であったわけではなく、こうして日陰者として生き続けている。アライバルも、確かにその日陰者としての顔を持っていた。だからこうして、魔術師ギルドの依頼写本などを携えている。
遠隔から印の刻まれた写本に文字を送信するのは、転送魔術の初歩の初歩だが、それが数千冊にも及べばちょっとしたものだ。その中の一冊を手にしているということは、アライバルが魔術師としては認められた存在である、ということを表していた。ただし、精緻な魔術によって次々と描かれていく文字を目で追うアライバルの表情は、憂鬱そのものだ。
「……ン」
不意に手を止めて、アライバルはズボンのポケットから携帯端末を取り出した。事務所への依頼の電話か、と一瞬期待に胸を膨らませたが、それはすぐにしぼんでしまう。見覚えのある名前だった。……魔術師の。
「……はい、こちらアライバル探偵事務所」
《
取って付けたようなあいさつの後に、早口の英語が続く。画面には、金髪碧眼の若い女が映っていた。
エマリー=エメリッヒは、新進気鋭、やり手の魔女だ。彼女がまだ幼い頃、当主であった父親を喪って傾きかけたエメリッヒ家を、たった十数年かそこらで持ち直したという才媛で、つまりは野心のたっぷりある女だった。魔術師にしては機械文明にも理解があり、こうして連絡を取ってくることがあった。
「何の用だ、エマリー? 冷やかしなら勘弁願うぜ。何せ、今から事務所の危機を救おうとしてたんだ」
《レオナルド、あなたまたギルドの仕事を安く請けようとしてたの?》
「レオン。レオン=アライバル」
ことさらにしかめ面をして見せて、アライバルはエマリーの言葉を訂正した。画面の中で、エマリーは額を押さえて、ゆるゆると首を振って見せる。
《何度でも言うけど、本当にあなた評判悪いんですよ。グラナダ・バルガス家の当主が魔術師ギルドでダンピングなんてしたら、若手は商売あがったりなんだから。
探偵のプライドだか何だか知らないけれど、仕事を受けるんだったら適正価格で受けてもらいたいものね。そうすれば、探偵事務所だってこう頻繁に経営難には陥らないでしょ? ねえ、レオナルド?》
「レオン=アライバル」
再度、訂正する。
探偵を始めた時から、アライバルは元の名前を名乗るのをやめていた。単純に実家の名前を名乗るのが嫌だったから、と言うのもあるが、元の名前で事務所を出していると、探偵と言っているのに魔術関連の仕事が山ほど舞い込んでくるからというのもある。
「俺はもう家と縁を切ったといつも言ってるんだ。家柄を気にするギルドの連中のほうがしいとは思わないかい?」
《縁を切るも何も、あなたが跡を継ぐって宣言したんじゃない》
「そりゃ、地下室に閉じ込められて子供作りに専念させられるのは避けたかったからね。今はもう自由の身だ。何の関係もない」
《親の財産を勝手に売って事務所を構えたのに?》
アライバルは大きくため息をついた。エマリーの言っていることは一から十まで正しいが、常に棘で刺そうとしてくるようだ。
エメリッヒ家は元の当主を喪ったことでその名が地に落ち、エマリーの手によって再興した。有能な彼女は家名を上げる意欲になお溢れている。家を放り出して探偵稼業を始めたアライバルのことが、理解できないし気に食わないのだろう。
「エマリー、頼むからそろそろ本題に入ってくれないか。
君も何も、俺をねちねち言葉責めにするために通話をかけてきたわけじゃないんだろう? 美人に攻め立てられるのは悪い気はしないけれど、さすがにばつが悪くなってきたところだ」
《――そうね。不毛だものね。レオナルド、魔術師としてのあなたに依頼があります》
言葉とともに、端末にエマリーからメールの着信があった。アライバルは呆れ返ったようなエマリーの顔を画面から消して、メールアプリを立ち上げる。
記載されていたのは、ウェブサイトのアドレスと地図情報だった。
「これ、ゴシップ誌のサイトじゃないか」
《いいから開いてください。そういうニュースの中に、私たちが見るべきものがあるのは知っているでしょう?》
言われるままにリンクを開く。ページの見出しはこうだ――【呪われた村、死者が訪れ、村民たちは恐怖している】
「斬新なタイトルだ」
エマリーからの返事はない。さっさと続きを読めということか。
記事の内容も、いかにもらしいものとなっていた。山間の村を襲う怪奇現象のストーリーだ。夜の間に家畜が殺され、死んだはずの人間が家を訪い、墓地が荒らされている。夜に有志が見回りをしたが原因は全く分からない。
話は、人間に被害は出ていないものの、それも時間の問題かも知れない、と、不安を煽る言葉で結ばれていた。村の所在地は、スペインはグラナダの南東に位置している。つまり、ここから南東だ。
「……これ、吸血鬼かい? うちの国では珍しいな」
《私に分かるのは、かつてその村にギルドに所属していない魔術師が住んでいて、その家は今所有者がいないってことだけよ。動いてくれそうな魔術師の中では、あなたがいちばん近くで死ななそうだから》
アライバルは首を竦める。
研究を続けるうちに、魔術師がヴァンパイア化する事象というのは珍しくない。たいていは合法的に血液を調達しおとなしくやっているのだが、まれにかたぎの人間の目に触れるような粗相をするものが出てくる。
だが、そういう場合に魔術師ギルドが動くことはそう多くはない。不死者やそれに類するものに対しては、もっと鼻が利く連中がいて、たいてい魔術師の出る幕はないからだ。
……ただし、その魔術師の行っている研究が魅力的なものである場合、話は別となる。日向に馬脚を現した不死の魔術師からは、研究を奪う大義名分が生まれるためだ。
「目的は、研究設備の解析か?」
《丸ごと回収でもいいですよ。もちろん、〈神究会〉も動くだろうから、行動は迅速に。
でも、あなたならできるでしょう? 報酬も払いますよ。市場価格で》
「……分かった、明日行ってみるよ」
開きっぱなしだった依頼写本を閉じて、アライバルは首を振った。
「契約書を送ってくれ。
ただし、まっとうなフォーマットでよろしく頼むぜ。魔力に反応する透かしなんかは入れない体裁だ。事務所に、魔術が関わるものはできるだけ置いておきたくないからな」
魔術師として腕を買われる、ということそのものが、自分にとってはひどく気の塞ぐ話だが、背に腹は変えられない。それに、エマリーから直接受けた話であれば、魔術師として自分の名が売れることもないはずだ。
《オーケー、それではよろしくお願いいたします。いい報告を期待しているわ》
通話画面の中で、エマリーが満足げに微笑んでいる。
ぎらついた部分を抑え、もう少しだけでも舌鋒を収めれば、彼女はもっと多くの男にとって魅力的な女性であることだろう……と、アライバルは常々思っていたが、それを口にしたことはない。それがセクハラである、ということぐらいは心得ていた。
拍動に合わせるように、波のように激痛が襲ってくる。
辺りは暗く、冷たく湿っているのにも関わらず、額には脂汗が浮かんで顔を伝っていた。先程から何度も気が遠くなりかけているが、痛みに合わせて意識が引き戻され、繰り返し呻いている。
いっそ気絶して、そのまま死ねば楽になれるのではないかと思ったし、先程から許しを請いたい気持ちでいっぱいだった。だが、言葉を投げかける誰かはここにはいない。
床から上へ向けて突き出した金属の杭が、前屈みになった脇腹を貫通している。できの悪い虫の標本のように、雑に床に縫い止められていた。もっとも、上から突き刺されたわけではなくて、杭が突き出しているところに、勝手に自分が落ちてきたのだが。
腹から流れ出した血と、血よりも流れ出てはまずい類の液体が混ざり合い、杭を伝って地面に液だまりを作っている。倒れ込みそうになるのを堪えて杭を握る手もまた、汗か血かでぬるついていた。靴の中もぐっしょりと濡れていて、それが果たして脂汗なのか、流れ落ちた体液で満たされているのかも分からない。とにかく、目も眩むような激痛に堪えかね、頭がうまく働かなか った。
常であれば、こんな痛みはとっくになくなって、そればかりか抜け出すのも容易であるはずだ。
だが、それはさっぱり叶わなかった。歯噛みしながら、改めて辺りを見回す。
暗く、狭苦しいこの小部屋の唯一の光源は、周囲の壁に刻まれた古風な魔法陣だ。杭を中心に取り囲むように描かれた四つの陣が、青い光を放っている。それが力の流れを阻害し、集中を乱し、自分をここへ繋ぎ止めたままにしていた。
限りなく、状況はよくない。
抜け出す方法は見当もつかず、このままでは失血して死んで行くだけだ。身体を尻から頭にかけて縦に刺されなかったことだけが不幸中の幸いだったが、単に苦しむ時間が延びただけとも言える。声を振り絞って助けを呼ぼうにも、助けてくれる相手のあてもない。声を上げたところで、ここへ自分を落としたものを愉しませるだけのような気がしていた。まさに、八方ふさがりだ。 手の打ちようもない。
苦痛か息苦しさにか、再び苦鳴を漏らし、上を仰ぐ。縦穴は上から塞がれていて暗く、何も見えはしない――
いや。
……見たくないものが見えた。
簡単な人探しだった。
借金を踏み倒して逃げた男の足取りを追い、聞き込みをし、文書の記録を調べ上げ、尾行をして居場所を確かめ、追い詰めていく。
まったくもって地味な、ともすれば退屈な手順ではあったけれど、その地道な工程こそ地に足の着いた探偵の仕事なのだ、とアライバルは信じた。
実際、完璧とはいえないまでも、確実な仕事運びであった、と断言できる。
今まで途中でこのじりじりとした作業に飽きて脱線を繰り返してきた反省が、今回のことに生かされていた。成長した、と思った。自分でも驚くほど集中していた。
もちろん、探していた人物が顔を変えた別人だったとか、素性だけを似せた全くの替え玉だったとか、追っている途中に殺されてしまって、それが大事件の端緒であったとか、追っている間はずっとそうした期待はしていて、そういうことはなかったわけだが。
とは言え、大躍進には違いない。アライバルは果たして依頼人が求めている男を探し出し、隠れ家にしているアパルトメントまでを確認した。それから、男が一人になるタイミングを見計らって、相手に声をかける――見つけて連れ帰るところまでが依頼人から受けた仕事の内容だった――抵抗されるかも知れないが、多少の荒事はつきものだ、と割り切っていた。いろいろあったが 、きっとこれが私立探偵・アライバルの、輝かしい実績の第一歩なのだ、と思っていた。
……声をかけた男が、アライバルを見た瞬間に顔を強張らせ、瞬間的に辺りに魔法のにおいを撒き散らすまでは。
「どうして、バルガス家の当主が俺なんかを?!」
「あああ」
男が懐から魔法陣の書かれた質の悪い紙を取り出してみせたその瞬間の、アライバルの落胆ときたらなかった。
依頼人がたばかっていたのか、知らずにたまたまアライバルに依頼したのか。分からないが、とにかく重大なルール違反だ。探偵の世界に、魔術師が入り込んでくるとは!
アライバルは向かってくる青白い炎を手を振るだけで霧散させると、あんぐりと口を開けて硬直する男に無造作に歩み寄る。その驚き方は、わざとらしいとさえ感じられた。男の手業は素早くもなく、正確でもない、稚拙と言ってしまっていい程度のものだ。特段、意識せずとも
顔を引きつらせ、男が慌てて背を向けて逃げに転じるのを、走って追いかけるのさえも億劫だった。
アライバルがやる気のない顔で軽く石畳を踏み鳴らすと、まろぶように駆ける男の足元から赤く光る鎖が幾条も伸び上がり、男の身体をあっさりと拘束する。
簀巻きにされて転がった男は、呪詛めいた言葉を喚き散らしたが、そのたびに鎖からあぶくのように魔法陣がほどけて浮かび上がり、結果として何も起こらなかった。己を戒める鎖に魔術を阻害されていることに気が付いた男は、見る見るうちに泣きそうな顔になり、やがてぐったりと脱力する。
アライバルは安堵の息を吐いた。人気のない路地であったのが幸いした。誰かに見られていたらたまったものではなかった。
「ば、化け物……」
「勘弁してくれよ」
力なく呻く男の言葉を遮るように、アライバルはかぶりを振る。項垂れたいのはこちらの方だった。
「何でこうなるんだ? こんなにまじめにやったのに!」
「おかしいと思っていたんだ。あんなに何重にも認識阻害をかけたのに、全部突破されて……あの女、どうやってこんな魔術師にわたりを付けたんだ……」
「頼むから、術を敷くなら俺に気付かれるレベルでやってくれ! 俺だって魔術師を相手に仕事をするなんて知ってたら、こんな依頼受けなかった!」
頭を押さえて、大きく息を吐く。
怒鳴っていても仕方がなかった。男の嘆きを信じるなら、依頼人はおそらくかたぎの人間だ。彼女にとっては運がいいが、アライバルにとっては最悪だった。
ふつうの人間に追われないように魔術だけを敷いて安穏としていたのなら、あっさり見つかるのは当然だ。隠れてさえいなかったのだろう。そもそも、未熟とは言え魔術師がただの人間から借金をして、踏み倒して逃げるとは。不景気もここに極まったか。
「……とにかくだ、受けた仕事は仕事だ。予定は狂ったが、あんたは依頼人のところに連れていく。
そのあとは……まあ、ちゃんと金を返すんだな」
アライバルは言い放ち、再び石畳を踏み鳴らした。男を拘束していた鎖が、ずぶずぶと男の身体の中に沈み込んでいく。
男は再び弱々しい悲鳴を上げたが、すぐに口を噤んだ。のろのろと立ち上がり、顔を引きつらせたままこちらに向き直る。
アライバルはひとつ頷いて、男に背を向けた。アライバルが歩き出すあとに、男が粛々と、抵抗もせずについてくる。アライバルはそれを振り返ることもなく、再び大きなため息をついた。依頼はこれでほとんど完遂だが、達成感はまるでない。
すっかり打ちひしがれて、アライバルは男を引っ立てて行った。
遅まきの昼食を終えてぶらぶらと事務所に帰ってきたアライバルは、無造作に開いた入口の扉をすぐさま閉めた。いるはずのない、いないで欲しい、絶対にいて欲しくないものが見えたのだった。
腹がくちくなり、若干の眠気を催した頭に指先で触れて、しばし考える。
部屋の中からは、何の物音もしなかった。見間違えでも幻覚でもないのなら、大人しく待っている男ではあるまいが、少なくとも今はこちらが現実を受け入れるまでの時間を取ってくれているらしい。
しかし、それもいつまでもというわけにはいかないだろう。
見なかったことにして再び外に出かけても、ここからいなくなる可能性は低い。それこそ、地の果てまで追ってきかねない。
そもそも、ここは自分の事務所である。明け渡すわけにはいかない。
「…………よし」
何とか腹は決まった。アライバルは顔を上げ、ドアノブに手をかける。
それから、できるだけゆっくりと、音を立てないように、恐る恐る開けた。
やはり、そこにいる。
レオン=アライバル探偵事務所は、いつも閑古鳥は鳴いているものの、少なくとも内装だけは事務所としての体裁を完璧に保っている。
シーリングファンライトに、デスクに、観葉植物。それから、客が来ないあまりふだんはアライバルの昼寝に使われているソファ。
そのソファに足をくつろげて座っているのは、亜麻色の髪を三つ編みにまとめた、信じがたいほど美形の男だ。
前に会った時に着込んでいた古風な剣士の服ではなく、この事務所の立地に合わせてか、二十一世紀のこの街並みに合った服装でいる。とは言え、どんな服を着ていても物騒には違いない。
男は、剣の聖者という名で通っていた。
探偵としてのレオン=アライバルではなく、魔術師としてのレオナルド=ルカス・ロサ・バルガスが身を置く日陰の世界において、絶対に近づくなとまで言われる特級の厄ネタのひとつだ。身体に無数の剣を収め、魔法のように取り出してみせる不死者。筋金入りの戦闘狂――
アライバルがこの男と出くわし、仔細あって戦う羽目になったのは、もう数ヵ月も前のことになる。
戦う、というよりは、一方的に痛めつけられて逃げまどい、何とか命は見逃してもらった、という方が正しいか。とにかくアライバルにとっては、この男とのことは思い出したくないレベルの
だが、いるものは仕方がない。勝てるはずもない相手なのだから、できるだけ距離を置いて話を済ませたい。
「……外出中に、鍵を勝手に開けて入るのは感心しないな」
ドアを開け放ったまま(もちろん、いつでもすぐさま逃げられるように)、アライバルは剣の聖者へ問いかける。
どうやって入ったのか――という問いは、恐らく愚問だろう。
先に言った通り、剣の聖者は体の中に無数の剣を収納している。その中にはいわゆるエンチャント、様々な魔術や呪いが仕込まれた代物も含まれていて、中のどれかに開錠の呪文でもかけられていれば、それで済む話だ。むしろ、剣で鍵を壊されなかったことを感謝するべきかも知れない。そういうことをしかねない男なのだ。
「どうしてあんたがここにいるんだ? 俺のところにわざわざやってきてとどめを刺しに来るほど、暇な身とも思えないんだけどな」
「ここは探偵事務所だろう。依頼のある人間がいてはいけないか?」
「……」
問い返され、アライバルは渋い顔で口を噤んだ。目を泳がせて、かぶりを振る。
「確かに、依頼人なら歓迎だ。が、あんたは俺に浮気調査や人探しや、ましてや警備や護衛なんて依頼するような奴には見えないね。あんたは、人を殺す側だろう」
「僕が殺すのは人間じゃない。人間だったものだけだ。お前のような」
こともなげに言って、剣の聖者は目を細めてソファから立ち上がった。アライバルが反射的に身構えるのを見て、口の中で笑い声を漏らし、
「だが、今日はお前を殺しに来たわけじゃない。依頼があるのは本当だ。こっちに来て話を聞くといい」
身を屈め、ガラス製のローテーブルの上に何枚かの写真を並べると、再びソファに沈み込む。
アライバルは逡巡した。
こうして距離を置いてはみたものの、実のところ、これはこの男相手には全く無意味な行為と言っていい。
入口からソファまで五メートル程度はあるが、相手はこの間合いからほとんど一息にアライバルの喉を切り裂くことができる。それをすぐさましないのであれば、本人の証言通りここで切ったはったをするつもりはないと考えていいだろう。前回も、この男はアライバルに対して嘘を述べたことはない。
不安なのは、前回――この男がアライバルを見逃した理由が、はっきりとは分かっていないことだ。
生かしておく理由ができ、殺す理由がなくなった、と男は表現した。後者はアライバルにもすぐに何のことか分かったが、前者については見当もついていない。
……だが、それはここで考えていても仕方がないことだ。
アライバルは嘆息し、後ろ手にドアを閉めると、剣の聖者の方へ向かって歩いて行った。向かい合うもう一つのソファに座り――本来は、依頼人と探偵の、座る位置が逆だ――テーブルの上に並べられた写真を覗き込む。
写っているのは、絵に描いたような城、それから、男だった。明らかに、隠し撮りめいた角度で撮ってある。何枚かあるが、すべて同じ人物のものだ。老年に差し掛かった頭髪の薄い男で、人相はそれほど良くない。人を信用できない人間の目をしていた。
「彼は?」
「アデラール=ペラン。
……何だ、お前の方が詳しいだろう? ここにも招待状が届いているはずだ」
言われて、アライバルは写真を手に取り、まじまじと老人の顔を見つめる。確かに、どこかで見覚えがある顔だ。
しかし、招待状というのは一体何の話だろうか。探偵として、パーティーに呼ばれるような功績はまだ立てていない。呼ばれるとすれば、もう一つの顔――魔術師として、ということになる。アライバルは首を捻りながら、記憶をひっくり返す。
そして、すぐに苦虫を噛み潰したような顔になった。
「……魔術師ギルドの重鎮だ。フランスはリモージュの名家で、後進の育成に熱心。人を集めてパーティーを頻繁に開いている」
「Si――お前はそのパーティーには一回も出席したことがないらしいな。いい機会だ。行ってくるといい」
「……何だって?」
「パーティーに入り込んで、この男のことを調査しろと言っている。そういう依頼だ」
ソファの肘掛けに頬杖を突き、剣の聖者はにやりと笑った。
どちらが探偵なのやら、この男はアライバルの素性や素行をある程度調べ上げてここに来ているらしい。そういえば以前去り際に、名乗ってもいない家名でこちらを呼んでいたような覚えがある。
アライバルの生家であるグラナダ・バルガス家は、長く続いた血筋の尊ばれる魔術師社会において、それなりに存在感のある家だ。魔術師ギルドの重役が、とりあえず当主を招待しておこう、と思う程度には。
しかも、アライバルは日銭稼ぎのために、魔術師ギルドから貸与される依頼写本を所持している。この探偵事務所に招待状が届いていてもまったくおかしくはない。調査を行うためにわざわざ潜入するのではなく、近づきやすいものを選別するというのも、まあ自然な話だろう。
しかし、剣の聖者がそういった正当な――まだるっこしい――方法を取るような男かと言えば、アライバルはそうは感じていなかった。
「あんたが行って、剣を突き付けていろいろ聞き出すんじゃないのか?
この、セニョール……ペラン氏に、不死者の疑いがかかってるってことだろう。あんたが動くということは」
剣の聖者、そして彼が所属する研究機関である〈神究会〉は、人間以外の生物を登録・捕縛・拉致・研究・虐待し、人間のもとに管理することを目的として動いている。それ以外で動くことはほとんどないため、わざわざこの男がここに来るならば、当然その件のはずだ。
だが、剣の聖者はあっさりとかぶりを振った。
「いや、それとはまた別口だ。
それと、僕はそれでもいいんだが、会長に止められている。確証が取れるまでは、ギルドと真っ向からことを構えるようなことは避けたいらしい。
もちろん、確証が取れたらそうするつもりではある」
「……悪いが、俺にも依頼を選ぶ権利というものがある。魔術師連中には関わりたくない。正直なところ、顔を見るのも嫌だ。
言っておくが、そこまでになったのはつい最近だぜ。魔術師の依頼を受けて、あんたに痛い目を見せられたせい……」
「こっちは金を用意している。それなりの金を。この事務所の経営が万年悪いことぐらいは把握している。
魔術師らしい仕事を受けるよりは、探偵らしいいい仕事だと思うが?」
アライバルは再び沈黙した。本当によく調べてきている。
確かに、エマリーからの依頼を達成したことでいったんは事務所は立ち直ったものの、結局あれから依頼はほとんど来ていない。この前の依頼も、経費分以外はほとんど金をもらっていないし、またそろそろ別の仕事をしなければいけないと思っていたところだった。
「それに」
ソファの背もたれに身を預け、剣の聖者は部屋の中を見回す。
「ここで命を張りたくはないだろう。せっかく立派な探偵事務所だ」
「結局、脅迫かよ……」
アライバルは深々と嘆息した。
脅迫。しかし、有効な脅迫だ。
ここで剣の聖者に暴れられて、事務所が血塗れのぼろぼろになったら、低空飛行の――ほとんど地に足がついている――経営に、いよいよもってとどめを刺されてしまう。
「…………分かった」
逡巡ののち、アライバルは呻くように言って頷いた。
「だが、調べる内容による。確かに俺は探偵だが、魔術師崩れでもある。ギルドをぶち壊しにするようなことは、人情としてしたくない」
「それは心配ない。むしろ、それを防ぐために行ってもらうと思っていい。
つまり、この男が今何を研究し、何をしようと考えているかが知りたい」
「超弩級のタブーだ、それは!」
こちらがいきなり叫んでも、剣の聖者が表情を変えることはなかった。アライバルは眉根を寄せ、
「あのなあ、門外漢のあんたには分からないかも知れないが、魔術師にとってまだ公表してない研究っていうのは、自分の親兄弟にさえ絶対に見せないもので、それを探ろうとするなんてのは最悪の……」
「探偵なんだろう? 魔術師じゃない」
話を遮って投げかけられた剣の聖者の言葉に、アライバルは唸り声を上げる。
魔術師のパーティーに潜入し、主催者の研究内容を調べるというのは、まず間違いなく探偵の仕事にはならない。研究内容を秘するために、研究設備ばかりではなくその周りの建造物、資料や、魔術師自身にさえ何重にも魔術的な仕掛けを施してあるのが一般的だからだ。魔術師ではない剣の聖者とは言え、さすがにそれを分かっていないはずはない。いけしゃあしゃあとよく言ってくれる。
だが、事務所や自分の命がここでいきなり脅かされるのはどうあっても避けたかった。剣の聖者はアライバルに選ばせる体裁をまだ保っているし、アライバルもそれに倣っているが、実際は選択権などない。あとは、アライバルが頷いてみせるかどうかの話だ。
金を払ってくれるだけ、あるいは探偵の仕事だと念を押してみせてくれるだけ、マシと思うほかなかった。剣の聖者がそうした態を繕っているのが、こちらを慮っているためなのかは分からないが。
「……くそ、了解だ。あんたの依頼を受けるよ。剣の聖者。
でも、書類にはなんて名前を書けばいい? まさか、St.Espadaとはいかないだろう」
「セルジオ=ステファネッリとでも。それと、依頼料は――」
提示された額面は、アライバルにとっては十分すぎるほど魅力的だった。
……もっと安くてもいい、とは言えなかった。機嫌を損ねて首を刎ねられては困る。
「それじゃあ……いい報告を期待している」
契約書に記入するための必要事項を聞き出したところで、ステファネッリ――依頼人としてそう名乗られた以上、そう称するべきだろう――は立ち上がり、大股に事務所から出ていこうとする。アライバルは立ち上がり、それを見送るように入口を振り返った。
「ひとつ、聞いてもいいかい、セニョール・ステファネッリ」
背を向けたまま、ステファネッリは足を止める。アライバルは息を吐いて、喉元にせり上がってきた緊張を散らした。一拍を置いて、言葉を続ける。
「――あの時あんた、どうして俺を生かしておくつもりになった?」
問いに、ステファネッリはくるりとこちらを振り返った。口元に笑みを浮かべ、どこか夢を見るような顔になる。見た覚えのある表情だ。
その時と同じように、男は首元へ指先を持ってきてみせた。
前回と違うのは、その白い喉元が布を引き下ろすまでもなく曝されていることと、そこにはもう、傷の残っていないこと。
「次は、僕を殺せるかも知れないからだよ、レオナルド――僕の首を、次は落としてくれるかも知れないからだ」
甘ったるい声音に怖気が走る。つくづくこの男はまともではない。この仕事が終わったら可及的速やかに関係を切って、もう二度と会いたくない。
ステファネッリはそれ以上何も言わずに、踵を返して事務所を出て行った。どっと疲れが襲ってきたのを感じて、ソファに沈み込む。
「……俺の名前は、レオン=アライバルだ。探偵として扱うなら、ぜひそこも徹底してくれ」
思い出したように――聞こえないのを承知のうえで――訂正すると、アライバルは背もたれにぐったりと頭を置いた。
より人気のない道を、より入り組んだ道を。
石畳の舗道を、ただひたすらに逃げていく。
いつからこうして走り続けているのか判然としない。すっかり汗だくで、息が上がり、眩暈がして、心臓が爆発しそうだった。
それでもよろけて覚束ない足を止められないのは、背後から迫ってくるものに、決して追いつかれてはならないからだ。
――以前にもこんなことがあったような気がする。だが、それが現実にあったことなのか、それとも切り捨てられた可能性の一葉であったのかは、とっくに分からなかった。
逃げ切れないことは理解している。
にもかかわらず自分がこうして足を動かしているのは、死への恐れがあるからだ。絶対に逃れ得ないものへの恐怖が。
汗に濡れたシャツを掴んでみても、
けれど、傷ひとつ負っていなくとも、すでに全身を突き刺されたような激痛が襲っていた。
それが長いこと全力疾走をしていたつけであるとか、緊張や想像や、妄想ではないことを知っている。
いや、果たしてそれは本当に、妄想ではないのか。
「……ッ!」
どこかに足を引っかけたのか、それとも単にもつれただけか。気が付けばバランスを崩し、走る勢いそのままに石畳の上にすっ転んでいた。
ぜえぜえと息をつきながら身を起こしても、一度止まってしまえば、もう立ち上がって走り出す気力は少しも残っていない。石畳で擦ったところにはいくつも細かい傷ができているはずなのに、痛いのかどうかさえ感じられず、傷口に潜り込んだ小石であるとか、滲んだ血であるとかをいちいち確認する気にもなれなかった。
だれに対してのものかも定かでない罵倒が喉元まで無数にせり上がる。しかし、出たのは結局咳だけだった。そして咳き込んだ途端に、いったい何を言うつもりだったのかも、すっかり霧散してしまう。
それでも、何とか立ち上がり、一歩足を進めた。ただ、頭の中には恐れだけがあって、なぜこんなことになったのかもうまく思い出せない。
よろめいて傾ぐ体を何とか踏ん張って支え、ふと足元に目を向けると、石畳の上にこびりついたわずかな血と汗から、眩しく感じるほどに真っ白い羽根が生え出していた。
――逃げることはない。
頭の中で響いた声を振り払うようにかぶりを振り、何とか走り出そうとする。もはや、足は満足に動かなかった――逃げることはない。
その声が、何を言わんとしているのか、よく分かっていた。思い通りになってたまるか、とも思った。
だが、意識はもうほとんど飛びかけていて、自分が今どこにいるのかも定かでない。何かを、どうにか、何とかしなければならないと思うものの、それを考える頭も時間もない。
肩口に走った衝撃と痛みを、待ちわびていたような気さえした。
息を詰まらせながら、かすんだ目を向けると、肩に剣が突き立ち、刃の潜り込んだ肉の隙間から、なお白い羽根がこぼれだしてくるのが見える。
振り返らなくても、その剣を投げたのが何者なのかを知っている。
それでも、震えながらも、背後を振り返った。
通りの向こうから悠然と現れたのは、時代錯誤な剣士風の格好をして、手に剣を携えた男だ。
その整った顔には、はっきりと失望の色がある。
それはひどく屈辱的な、そして絶望的な、どんな言葉を投げかけられるよりも明確な最後通牒だった。
痛みに耐えながら、男へ指先を差し向けても、何も起こることはない。
表情を変えぬまま、立ち止まった男がわずかに身を沈める。
その小さな動作だけで、腹に、足に、腕に、次々と衝撃が走り、剣が突き立てられていく。激痛に脳髄が攪拌され、閃光に塗り潰される。
悲鳴さえ上げられなかった。
ただ、男に何とか焦点を合わせようとすると、視界いっぱいに銀色の光が広がって――
けたたましい着信音で目が覚めた。
今いるのが間違いなく自分の事務所であることを確認すると、来客用のソファにだらしなく沈み込んだまま、のろのろと手元の携帯端末に手を伸ばす。
画面に表示されているのは見覚えのない番号。つまりは、新しい依頼人からの電話であることを示していた。大きくため息をついて、通話のボタンをタップする。
「はい、こちら、レオン=アライバル探偵事務所――」
呻き声を上げるのを何とか堪えて、アライバルは額を押さえながら声を押し出した。探偵として、最低限、礼儀を失していない程度の声音は出せていたように思う。
相手は、やはり依頼人だった。あなたの評判を聞いて、ぜひ依頼したいことがある。詳しい話は直接会ってしたいので、会う時間を相談させてくれないだろうか、云々。
再度のため息は何とか噛み殺して、アライバルはソファに手をつくと、おもむろに身を起こした。
何をどう話し、何を伝えるべきなのか、頭の中でぐるぐると考えて、慎重に言葉を選別する。
何を話すべきか。
探偵として依頼を受けなければならないのだから、まずは会うことを了承するべきだ。
そして、予定を確認する必要がある。自分が間違いなく入れている、現実の予定をだ。
依頼人に少し待つように伝えると、アライバルは携帯端末の予定表を立ち上げた。
表示された画面に覆いかぶさるように別の映像が見えてくるのを、ゆっくりとまばたきして打ち消す。何度やっても、労力のかかる作業ではあった。
「……はい、そうです。本日の三時からお会いできます。
ええ、問題ありません、すぐに伺いますので……」
薄氷を踏みしめるような感覚で、恐る恐るにそう伝える間にも、目の前には今見えるはずのない情景が再生され続けている。
依頼人が何を依頼しようとしているのか、これから何が起こるのか、どうすれば依頼を果たすことができるのか。
それらがすべて分かった状態で今から依頼人に会おうというのは正気の沙汰ではなかったし、どう考えても探偵の仕事ではない。
だが、迂闊に振る舞って、せっかく上がった評判を下げ、事務所を畳む羽目になってはたまらない。
それに、今は別の目的もあった。
「はい、ありがとうございます。それでは、のちほど……失礼します」
力なく応答し、アライバルは憔悴した顔で通話を終了すると、頭を抱えて深呼吸する。
脳を軋ませながら、これから起こり得る未来の体感が、じわじわと体を襲い始めている……だが、そこに自分の死ぬ姿は見当たらない。
よし、と小さくつぶやいて、アライバルはソファから立ち上がり、事務所の中を見回した。
ここのところ依頼を立て続けにこなしているレオン=アライバル探偵事務所は、しかしおおむねいつも通りだった。
天井で回るシーリングファンに、本棚にデスク、コピー機に応接用の低い机、向かい合って置かれたソファ――ひとつは、さっきまで寝台にしていたが――それから、眠っている間にソファの下に舞い落ちた、何枚かの白い羽根。
「…………」
アライバルは渋い顔で、ソファの横に置いた小さな箒とちりとりを手に取った。
この程度であれば、ちょっとした魔術であっという間に片付けることもできるのだが、ここは探偵事務所で、自分は探偵だ。むやみに魔術を使うことは避けたかった。……探偵が、体から次々羽根を生やして床に散らかすか、というのは、話が別として。
とにかく、依頼だ。
今の自分は、接触面を増やす必要がある。
打ち合わせを終えてビルから出てきたアライバルは、傾いた日に照らされた大通りを見回して、今日何度目かの憂鬱なため息をついた。
依頼はごく複雑な、本来であれば長い期間を設けて臨まねばならないような、依頼人の会社に関する調査だった。
だが、調査が必要な項目から、どこを調べるべきか、その結果に至るまで、アライバルはすでに詳らかに知ってしまっている。
知ってしまっているが、打ち合わせを終えた後にしたことは、怪しまれないように依頼を受けて、結果を伝える期限について約束をしただけだ。
自分にもう少しこだわりがなければ、名探偵の言葉を借りて――初歩的なことだとでもうそぶきながら――依頼人にすべてを教えたのだろうが、それは主義に反した。それは探偵の所業ではなくて、ただ予言者がいるだけだ。
そして、自分は予言者でさえない。
アライバルはバス停へ向かって歩き出しながら、大通りに点々と立つ並木や、行き交う車や人々に目をやった。
現実の像に重なって、彼らにこれから起こり得る未来の映像が、無数に視界の中に再生されていく。それを、自分でコントロールすることができない。
予言どころか予視。予視どころか、自分にこれから起こり得る未来の話に限って言えば、可能性が体感となって襲いかかってくる始末だった。先々のことを記憶として思い出し、体に再生され続けているような状態だ。
それはしかも、確定した未来ではない。揺らぎを繰り返し、辿り着くとも破棄されぬとも知れない、可能性の群れだ。
現実に外界と接触すれば接触するだけ、その枝葉は際限なく広がっていく。インターネットでページにアクセスした端から、それにかかわる巨大なデータをダウンロードされ続けているようなものだ。精神的なストレスももちろん、そもそも脳への負荷が尋常ではない。
「……」
袖口から零れ落ちた白い羽根を、アライバルは立ち止まって拾い上げる。
油断すればぼろぼろと皮膚の奥から生えだしてくる、この白い羽根。どう考えても、フランスで戦ったあの天使が落としていたあの羽根と同種のものだ。
天使はアライバルを指し、「あなたのことは最後まで
アライバルは、それをいわゆる遠隔視、遠見の類であると判断していた。遠くにあるものを監視するための魔術の中でも、使い魔のような端末を用いるのではなく、純粋な魔力でのマーキングによって相手の行動を確認するものだ。
この遠見に関して、アライバルは特に厳重に対策を施していた……そうでないと、私生活が親に筒抜けになるため……そのため、視えないのも当然だろう、ぐらいにしか考えていなかった。
だが、この状況に陥ってみれば、あの天使の言いたかったことはよく分かる。これほど正確な予知のことであったとは、想像もしていなかった。
考えてみれば以前、まだ起こってもいない事件について推理を披露してしまったことがあった。
ちょっと集中力が欠けていたとか、想像力の翼が羽ばたきすぎていた、ぐらいに考えていたのだが、それはまさに天使化の先触れであったのだろう。今や、自分はあの少年と同じように、頭の中から天使になりつつある。
どこからやってきて、どのようにして入り込んできたのかは分からない。だが、あの城で袖口から羽根が一枚落ちた時、確かに天使の声を聞いた――「身を委ね、楽になれ」というような。
いつから頭の中にいて、どれぐらいこちらのことを把握し、いつまでに身体を乗っ取るつもりなのかもまた不明だが、少なくともいずれ乗っ取るつもりであるのは確かなわけだ。そして恐らくはそのあとで、この予視を使って世界を滅ぼそうとしている。
剣の聖者は天使を指して、世界に投げかけられた呪いのようなものであると言っていた。
呪いというのは、装置だ。対象に黒く染みついて定められた不利益な効果を発揮する。世界を滅ぼすための装置。
呪い・精神汚染・催眠。そういうものに対して、アライバルは十全な備えをしているつもりだったが、相手に上回られたということか、それとも、ようなものというだけでそのものではないから、魔術では防ぎようのないものなのか。
あの城で、剣の聖者やエマリーからもう少し話を聞き出せればよかったのだが、すでに予視で、アライバルの天使化を察知した時点でこちらを殺しにかかってくるのが視えていたため、迂闊なことは言えなかった。
もっとも、剣の聖者が天使を剣の台座に仕立てていたり、エマリーがあっさり若い魔術師たちを殺す判断を下したのを見ていては、予視がなかったところで言い出せはしなかっただろう。ふたりとも、あまりに見限るのが早すぎる……だが、確かに天使というのは、それほど危険な存在なのかも知れなかった。
アライバルも、天使をどうやって自分から切除するか――殺すか、お帰りいただくかは問わないとして――手段を探してはいるのだが、予視の範囲をいくら広げても、見当もついていなかった。
このままいけば、あの少年のように天使に頭を乗っ取られる。その未来が視える。
そして、その先に何が待っているかと言えば……
「……クソッ」
今まさに胸元に剣が突き立てられたような灼熱感と痛みを感じて、アライバルは顔を歪めて立ち止まった。
見下ろせば、傷ひとつついていない自分の体に重なるようにして、くまなく剣の突き立てられた自分の胸ぐらが視える。そして治癒魔術を起動するまでもなく、傷の奥から剣を押し出そうとする力が働くのが。
このことが剣の聖者の知るところとなれば、この光景は現実のものになるだろう。あの男が嗅ぎ付ける前に、どうにかして頭の中の天使を排除しなければならない。
息をつき、アライバルは再び通りを歩き出した。
今まではひたすら接触面を増やし、予視の幅を広げて解決策を見つけようとしていたが、そろそろ次の段階に移るべきだろう。怖気づいて〈神究会〉や魔術師の方には全く探りを入れていなかったが、これ以上こんな探偵らしくない方法で事件を解決していくのはごめんだったし、探偵事務所をこのまま羽根まみれにしておくわけにもいかない。死ぬつもりもない。
であれば、一歩足を踏み出して、うまくやらなければなるまい。
アライバルは自分を鼓舞して、バス停へ向かった。
よれたスーツの生地ごと肩の肉を蜘蛛が食いちぎっていった。
こちらの頭ほども大きさのある、くろがね色の蜘蛛だ。
アライバルは苦鳴を上げながら、背にした壁を血しぶきが彩るのを、思わず目で追った。
壁と言っても、煉瓦や石でできたそれではない。
視覚上は、そこには何もない。しかし透明な見えない壁が確かにそこにそそり立ち、何もない空間に血がべたりと張り付いている。
「悲鳴なら、いくら上げてもらっても構いませんよ」
白い親指を口の端に当てて、金髪の美女が艶然と微笑んだ。
アライバルは返す言葉を選ぶように息をつきながら、壁へべたりと手を付ける。押したところでびくともしないそれは、昔ながらの古風な結界術だった。間違いなく、目の前の魔女が展開したものだ。
周囲に認識阻害をかけるだけではなく、この周囲十数メートルにわたって区画を物理的に遮断し、アライバルごと己を閉じ込めている。
――いや、正確には彼女自身はここにはいない。
女の足元へ目を向けると、細身のパンツの足元が、蜘蛛と同じ鉄色に染まり、そこから小さな蜘蛛が無数に湧き出しているのが見えた。
遠隔地へ強固な結界を張りながら、その中の端末にさらに指示を出しているのは、さすがの精緻さ、周到さだった。間違いなく、ここでアライバルを殺すつもりなのだろう。
「君と――殺し合うつもりはないんだが、エマリー」
「もちろん、分かっているわ、レオナルド。
でも、殺し合いにはならないでしょう?」
エマリーがそう問いかけてくるとともに、痛みや失血でなしに目が眩み、自分の死の可能性が脳に叩き込まれてゆくのを感じた。
生身の自分と端末を置いているだけの彼女では勝負にもならない。エマリーの問いは全く正しい。だが、わざわざそれを肯定する余裕もない。
アライバルは足を踏ん張りながら、肩口からゆっくりと手を離す。そこにはもはや傷は残っていない。服だけが直らないまま、間抜けに肌を晒している。
「……君は、不死になるつもりがある?」
その問いの答えを、アライバルはすでに知っている。だが、わざわざ口に出す気にはなれなかった。エマリーは首を傾げて、軽く肩を竦めてみせる。
「まさか。そんな不自由ないきものになる必要はないわ。
あなたもそう思っているんじゃない?」
「ああ、まったくその通りだ……」
アライバルは苦笑した。そうするうちにも、エマリーの姿を構成していた小指ほどの小さな蜘蛛の群れが、数える気力も失せるほどの数、こちらの体表を埋め尽くすように足元から這い上ってきている。
蜘蛛たちはアライバルの身体を登攀しながらも、互いに癒着と分離を繰り返し、その大きさを変幻に変えながら、皮膚へと牙を立てていった。皮膚が突き破られ、肉が食いちぎられる痛みが繰り返し、繰り返し襲ってくる段に至って、アライバルはさすがに悲鳴を上げる。
「こんなものを喰って、腹を壊すんじゃないのか!」
声に怯えが滲んでいるのは、自分でもよく分かっていた。蜘蛛に食いちぎられた端から体が再生し、それをさらに蜘蛛が食い破る。そしてやがて、再生の速度を追い越そうとしている。それにもかかわらず、死ぬことはできない。
肉の中に潜り込んだ蜘蛛の牙が、脚が、神経をずたずたにし、骨を引っかく痛みに、アライバルはもはや声を失って膝を折った。
うつぶせに倒れた視界を、あっという間に蜘蛛が埋める。抵抗する気力もなく、ただただ苦痛だけが頭の中を白く塗り潰していった。
だが、一匹の蜘蛛が眼球に牙を突き立てた瞬間、視界が真っ赤に染まり、自分の皮膚の内側から、蜘蛛を押しのけるように翼が生え出す。
そこまでは、分かった。
《……レオナルド?》
「ああ、いや……
すまない、ちょっとぼうっとしていた。最近暑いだろ? なんだかよく眠れなくてね。
それと、繰り返しになるんだけど、できればレオン=アライバルと呼んでくれると嬉しい」
耳に押し当てた携帯端末のスピーカーから、呆れたようなため息が聞こえてくる。
アライバルは幻の苦痛、可能性の体感に滲んだ涙をこっそりと拭った。
羽根もすっかり掃除されて、変わり映えのしない事務所が視界の中に収められている。
何も起こってはいはしない。ただ、エマリーに電話をかけて、少し話を聞いているだけだ。それでもいくつか選択を間違え、エマリーに察せられてしまえばあの通り……アライバルは身震いすると、来客用のソファに深々と沈み込んだ。
「それで、やっぱり電話では教えてもらえないかい?
この前のこと、どうしても頭に引っかかっていてね……できるだけ、天使とやらについて詳しく教えてもらいたいんだが」
《確かに、私の依頼人からは口止めされてはいないけれど、
直接会うのは難しいですけど、蜘蛛なら今そっちの国で仕事をさせているから、終わったら向かわせましょうか?》
「いや、それには及ばない……」
額を押さえて、アライバルはがっくりとソファの肘掛けに頭を投げ出す。
エマリーの端末から天使化を隠し通せる可能性は限りなくゼロに近かったし、ばれたが最後どんな目に遭わされるのかももうすっかり分かっていた。もし生き残るのを諦めて死に方を選ぶ羽目になったとしても、エマリーに殺されることだけは避けたい。
「一応、近くに〈神究会〉の知り合いもいる。そっちと会ってみるよ」
《その方がいいと思いますよ。私もそれほど詳しく知っているわけではありませんから》
詳しく知っているわけではないのに問答無用で殺すのか、それとも詳しく知っているわけではないからこそ問答無用で殺すのか、と、恨みがましく問いたい気分だったが、それをアライバルは何とか堪えた。起き上がって、放り投げていたジャケットを拾い上げる。
「そうだ。そういえば、君ってタコは好きかい?」
《勘違いされがちだけど、ゲテモノを食べる趣味はないの……あら、そっちではふつうに食べるんでしたっけ?》
「ああ、君が嫌じゃなければ、君本人が遊びに来た時にうまい店を紹介するよ。
そうなんだよ、俺が今から会おうって男は、可哀想なことに金輪際タコが食えないんだ。君って彼のことは知ってるかい? 知らなかったら彼のことも紹介しよう、面白い話があって……」
《もう、切っていいですか?》
テーブルの対面で男が渋面を作っている。
黒い縮れ毛と青い目が印象的な若い男で、小柄ながらも鍛えられた体をしているのが分かる。年齢はアライバルと同じか、少し年上ぐらいだろう。椅子に浅く腰かけて両手で頭を抱え、テーブル上、アライバルの目の前に置かれたできたてのパエリアを睨み付けている。
男の名前は、ドナート=ポッラローロといった。
「パエリアは、俺がこの世で一番嫌いな食い物だって言ったはずなんだよな……」
憂鬱そうな顔でそう呻いたポッラローロの顔を見やりながら、アライバルは大皿から直接、米をスプーンですくい上げる。
食べる前から舌の上にその美味さが広がり、腹がくちくなったような気がして奇妙な気分になりながらも、口にスプーンを運び、もう一方の手で軽くメニューを叩く。
「別の料理もある」